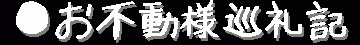

| ● | 巡礼は、古くはインドの仏蹟巡拝に端を発し、お釈迦様入滅の後、お釈迦様降誕の地、悟りの地、 | |||
| ● | はじめて説法された地、涅槃に入られた地等、仏教徒がその聖地を巡りながらその過程でお釈迦様の遺徳を | |||
| ● | 偲び、自分自身を見つめ直し、救済し、再び蘇らせるために始まったと言われております。中国においても | |||
| ● | 古来から観音信仰がさかんであり、観音信仰の手段として巡礼は民衆信仰の中心を占めたと言われます。 | |||
| ● | 日本では飛鳥時代に中国から伝来した観音信仰が特にさかんとなった平安中期から、修験者や僧たちの | |||
| ● | 修行の中に取り入れられ、始まったとされました。江戸時代になると巡礼は、修行という意味よりむしろ | |||
| ● | 布教の方法として勧められ庶民の中に浸透し、著しく広まりました。 日本各地においても数多くの巡礼 | |||
| ● | 霊場があり、特に四国八十八箇所の「お四国参り」や西国三十三箇所及び坂東三十三箇所、秩父三十四 | |||
| ● | 箇所の「百観音霊場巡り」は有名ですが、そのうち平安末期の仏教説話集の今昔物語集や後白河法皇が | |||
| ● | 編んだとされる歌謡の梁塵秘抄の中には四国巡礼の様子が描かれております。 | |||
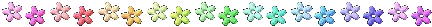
第1回 目黒不動尊(東京)
第2回 目青不動尊(東京)
第3回 目白不動尊(東京)
第4回 等々力不動尊(東京)
第5回 田無不動尊(東京)
第6回 薬研堀不動院(東京)
第7回 日吉不動尊(神奈川)

